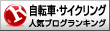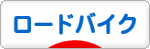5泊6日の高知旅行で海水浴した結果、年甲斐もなく背中が日焼けしてしまった結果、背中の皮がめくれて部屋中に散乱していることについて、たーちゃん@妻からクレームを受けているのですが、猫の毛は良くて、旦那の背中の皮は許せないその理由についてくわしく事情を説明していただきたいたーちゃんです。おはようございます。
自転車ブログ集を見るならここをクリック(自転車ブログ村)
ロードバイクブログ集を見るならここをクリック(ロードバイクブログ村)
自転車ブログ集を見るならここをクリック(自転車ブログランキング)
結婚した当初、ヨメは背中の皮を向いてくれていました。
それが12年後、まるで汚物のように扱われています。
背中の皮という、私の視界に入らない部位のことまで責任を取ることはできません。
かつお節のような背中の皮が落ちていることぐらいで目くじら立てて怒ることではないでしょう。
家族のために、朝の早よからロードバイクに乗って、山を登ってから仕事に行っているのです。
もう、堪忍して下さい。奥さん。
もう30歳代後半になると、ラッシュガードなるものを着ないといけないのでしょうか?
ムスメを市民プールなどに連れて行くと、ラッシュガードを着ている人のなんて多いことでしょう。
家族サービスとして、市民プールに行った時の楽しみといえば、小さな子どもを連れてきている30歳代奥さまの水着姿を眺めることしかありませんよね。ご主人。
そんな楽しみを、われわれサラリーマンサイクリストから奪い取るラッシュガードなんて、決して身につけることは無いと思っていたんですが、やはり紫外線には勝てません。
来年はラッシュガードを身につけて、以後、部屋中に背中の皮が散乱しないように気をつけます。
さて、チューブレスタイヤについてお話する前に、レース後、私たち家族がどうなったのか少々お話したいと思います。
↓お決まりのポーズをユニクロのボロボロウインドブレーカーを身にまとって
![]()
昨年の乗鞍ヒルクライムでは“おひとりさま”だった私は、ゴール後、誰からも健闘を讃えられることも無く、見知らぬ人にお願いして写真を撮ってもらって、そそくさと下山していました。
しかし、チームサカタニに入った今は違います。
ゴールでは、毎週、日曜日の朝早くから、水越峠を登り降りしながら汗を流したみんなと達成感と充実感を共有し、ペットボトルのコーラで乾杯しておしゃべりをしていたので、下山が遅くなったのです。
auの電波は乗鞍山頂でも入るらしく、ヨメから「今どこ?」という電話がかかってきました。
下山後、宿に向かっためんめんと別れた私は、乗鞍ヒルクライム後のお楽しみである「冷えたスイカ食べ放題」も乗鞍ガールとの記念撮影もすることなく、妻子が待つシエンタの元へ直行。
そそくさと着替えを済ませ、そびえる乗鞍岳に向かって「来年は1時間ヒトケタで登ってやる」と誓いつつ、乗鞍高原を後にしました。
安房峠トンネルを超え、一路、私たちは飛騨の小京都「飛騨高山」に向かいます。
朴葉みそ定食の昼食後、古い町並みを散策したのですが、古い町並みにある酒蔵での日本酒の試飲を楽しみにしていた、たーちゃん@妻は「これは、辛口や」とか「これは飲みやすい」などと評しつつ日本酒の地酒をグビグビ。
その結果、以後の自動車の運転は私がしなければらなず、大阪に到着したときはバタンキューと相成ったわけです。
かくして、私の乗鞍はこれで終了したのですが、いろいろ課題が分かりました。
これからも早朝ヒルクライム自転車通勤し続けることができるモチベーションができたことについては、価値あるレースだったと思います。
さて、チューブレスタイヤについてお話を戻しましょう。
ロードバイクのタイヤについては大きく3つに分類されます。
タイヤそのものが筒状になっているチューブラー。
ママチャリと同じように、中にチューブを入れて膨らませるクリンチャー。
そして、クリンチャータイヤからチューブを取り除いた「チューブレスタイヤ」の3種類です。
マウンテンバイクのホイールではチューブレスタイヤは以前からありましたが、ロードバイク用のタイヤではそれほど歴史はありません。
製品として過渡期のものらしく、まだ一長一短あるので、その評価は賛否両論分かれています。
“長所”としては、チューブが入っていないので、チューブとタイヤそのものの摩擦抵抗が無くロスが少ないとか、チューブが無い分、軽量化できるそうです。
それに加えて、バーストするリスクが極めて低いので安全性が高いとか、チューブがないので、リム打ちパンクが無く、低圧でも走行することができるメリットも無視できません。
↓いい眺めやなぁ〜
![]()
しかし、“短所”としては装着するのが難しく、ブログでは「死ぬ思いをした」とか、「装着するのを諦めた」など言われています。
ロングライドなどでパンクした時は、中にチューブを入れたらいいそうですが、それだとチューブレスタイヤのメリットが少なくなってしまいます。
そんな賛否両論別れるチューブレスタイヤですが、今回、私が使ってみた感想についてこれからお話しましょう。
まず、チューブレスタイヤを採用したきっかけですが、以前、ブログでお話したことがありますが、早朝ヒルクライム自転車通勤中、前輪がとつぜんバーストしたことがありました。
幸い、落車することは免れましたが、フロントホイールのリムがボロボロになったのです。
ホイールはwiggleでポチッとしたシャマルウルトラ2−wayfitですが、サカタニ滝谷駅前店の店長さんに相談した所、リムを交換することになりました。
そしてタイヤもバーストしてしまったので交換しなければなりません。
はじめは使い慣れていて耐久性も高いコンチネンタル・グランプリ4000sにしようと思っていました。
ところが、店長のカツさんから「チューブレス兼用ホイールは、チューブレスタイヤを履かせるべき」とアドバイスを受けたので、初めてチューブレスタイヤを採用することにあいなったのです。
チューブレスタイヤのデメリットである装着性の悪さも、カツさんに装着してもらうので無問題。
どのタイヤにするのかはカツさんにお任せすることにして、それまでの間はR500で修行の旅。
乗鞍に向けて出発する前日、前後輪ともチューブレスタイヤが装着された状態のシャマルウルトラとご対面。
同時に、後輪のフレ取りと、ハブのグリスアップもお願いしていたので、実質的にはホイールのフルメンテナンスと言っても過言ではありません。
↓乗鞍の山頂で六甲おろしを歌唱する。
![]()
このとき、クアトロはチェーンを取り外していたので、電動アルテグラのチェックはできませんでした。
でも、「もし、明日、試走してみて調子が悪ければ、宿まで持ってきて。」と言ってもらっていたので不安に思うことはありません。
というわけで、乗鞍ヒルクライムの前日、チューブレスタイヤのシェイクダウン。
実際、チューブレスタイヤで走ってみると、とても不思議な感じ。
走行するときの抵抗感が感じられないというか、とても軽いんですよね。
私の場合、タイヤの空気圧は8気圧なのですが、リム打ちパンクのリスクが無いチューブレスも同じ8気圧に設定。
タイヤの気圧を高くすればするほど走行感が軽くなると思っていたのですが、高すぎると路面の接地性が低くなるので良くないそうです。
8気圧の場合、細かな段差でも振動となってハンドルに伝わってくるのですが、チューブレスの場合、「まったり」とした振動で伝わって来ました。
チューブレスは乗り心地が良いと言いますが、それはタイヤの空気圧を低くしても走れるためだと思っていたのです。
けれども、同じ8気圧でもチューブレスのほうが乗り心地が良かったのは想定外のメリット。
そしてレース本番。
ヒルクライムの登りもやっぱり軽い印象を受けました。
具体的に言うと、「このくらい回せば、このくらい進む」というのが誰にでもあると思うんですが、自分が思っている進み具合よりも+10%進むって感じでしょうか。
↓さあ、行ってきます。
![]()
早朝ヒルクライム自転車通勤でも使用したいのですが、あくまでシャマルウルトラは“決戦用”。
次のレースまでは封印しなければなりません。
というわけで、普段はR500を使うことにしました。
もし、落車したり、バーストしてホイールがお釈迦になってもR500だと精神的なダメージも、お財布のダメージも少ないでしょう。
それに、来年の乗鞍ヒルクライムで1時間ヒトケタ台を目指すためには、R500で自らに負荷をかけて鍛えあげなければなりません。
昔、少林寺三十六房という映画がありましたが、大阪府の秘境金剛山金剛寺に実在するという昼暗夢三十六房。
その第1房“鉄輪房”では、鋼鉄で組み上げられた車輪をひたすら回し、その心身を鍛え上げられるとか。(出典:民明書房刊「日本にも実在した少林寺三十六房」
というわけで、明日から前後輪とも鉄下駄R500を履いて一から出直します。
自転車ブログ集を見るならここをクリック
ロードバイクブログ集を見るならここをクリック
自転車ブログ集を見るならここをクリック
ランキングに参加しています。押して頂けると、更新のモチベーションが上がります!お手数ですがポチッっとクリックお願いします。
![にほんブログ村 自転車ブログへ]()
![人気ブログランキングへ]()
![にほんブログ村 自転車ブログ ロードバイクへ]()
自転車ブログ集を見るならここをクリック(自転車ブログ村)
ロードバイクブログ集を見るならここをクリック(ロードバイクブログ村)
自転車ブログ集を見るならここをクリック(自転車ブログランキング)
結婚した当初、ヨメは背中の皮を向いてくれていました。
それが12年後、まるで汚物のように扱われています。
背中の皮という、私の視界に入らない部位のことまで責任を取ることはできません。
かつお節のような背中の皮が落ちていることぐらいで目くじら立てて怒ることではないでしょう。
家族のために、朝の早よからロードバイクに乗って、山を登ってから仕事に行っているのです。
もう、堪忍して下さい。奥さん。
もう30歳代後半になると、ラッシュガードなるものを着ないといけないのでしょうか?
ムスメを市民プールなどに連れて行くと、ラッシュガードを着ている人のなんて多いことでしょう。
家族サービスとして、市民プールに行った時の楽しみといえば、小さな子どもを連れてきている30歳代奥さまの水着姿を眺めることしかありませんよね。ご主人。
そんな楽しみを、われわれサラリーマンサイクリストから奪い取るラッシュガードなんて、決して身につけることは無いと思っていたんですが、やはり紫外線には勝てません。
来年はラッシュガードを身につけて、以後、部屋中に背中の皮が散乱しないように気をつけます。
さて、チューブレスタイヤについてお話する前に、レース後、私たち家族がどうなったのか少々お話したいと思います。
↓お決まりのポーズをユニクロのボロボロウインドブレーカーを身にまとって

昨年の乗鞍ヒルクライムでは“おひとりさま”だった私は、ゴール後、誰からも健闘を讃えられることも無く、見知らぬ人にお願いして写真を撮ってもらって、そそくさと下山していました。
しかし、チームサカタニに入った今は違います。
ゴールでは、毎週、日曜日の朝早くから、水越峠を登り降りしながら汗を流したみんなと達成感と充実感を共有し、ペットボトルのコーラで乾杯しておしゃべりをしていたので、下山が遅くなったのです。
auの電波は乗鞍山頂でも入るらしく、ヨメから「今どこ?」という電話がかかってきました。
下山後、宿に向かっためんめんと別れた私は、乗鞍ヒルクライム後のお楽しみである「冷えたスイカ食べ放題」も乗鞍ガールとの記念撮影もすることなく、妻子が待つシエンタの元へ直行。
そそくさと着替えを済ませ、そびえる乗鞍岳に向かって「来年は1時間ヒトケタで登ってやる」と誓いつつ、乗鞍高原を後にしました。
安房峠トンネルを超え、一路、私たちは飛騨の小京都「飛騨高山」に向かいます。
朴葉みそ定食の昼食後、古い町並みを散策したのですが、古い町並みにある酒蔵での日本酒の試飲を楽しみにしていた、たーちゃん@妻は「これは、辛口や」とか「これは飲みやすい」などと評しつつ日本酒の地酒をグビグビ。
その結果、以後の自動車の運転は私がしなければらなず、大阪に到着したときはバタンキューと相成ったわけです。
かくして、私の乗鞍はこれで終了したのですが、いろいろ課題が分かりました。
これからも早朝ヒルクライム自転車通勤し続けることができるモチベーションができたことについては、価値あるレースだったと思います。
さて、チューブレスタイヤについてお話を戻しましょう。
ロードバイクのタイヤについては大きく3つに分類されます。
タイヤそのものが筒状になっているチューブラー。
ママチャリと同じように、中にチューブを入れて膨らませるクリンチャー。
そして、クリンチャータイヤからチューブを取り除いた「チューブレスタイヤ」の3種類です。
マウンテンバイクのホイールではチューブレスタイヤは以前からありましたが、ロードバイク用のタイヤではそれほど歴史はありません。
製品として過渡期のものらしく、まだ一長一短あるので、その評価は賛否両論分かれています。
“長所”としては、チューブが入っていないので、チューブとタイヤそのものの摩擦抵抗が無くロスが少ないとか、チューブが無い分、軽量化できるそうです。
それに加えて、バーストするリスクが極めて低いので安全性が高いとか、チューブがないので、リム打ちパンクが無く、低圧でも走行することができるメリットも無視できません。
↓いい眺めやなぁ〜

しかし、“短所”としては装着するのが難しく、ブログでは「死ぬ思いをした」とか、「装着するのを諦めた」など言われています。
ロングライドなどでパンクした時は、中にチューブを入れたらいいそうですが、それだとチューブレスタイヤのメリットが少なくなってしまいます。
そんな賛否両論別れるチューブレスタイヤですが、今回、私が使ってみた感想についてこれからお話しましょう。
まず、チューブレスタイヤを採用したきっかけですが、以前、ブログでお話したことがありますが、早朝ヒルクライム自転車通勤中、前輪がとつぜんバーストしたことがありました。
幸い、落車することは免れましたが、フロントホイールのリムがボロボロになったのです。
ホイールはwiggleでポチッとしたシャマルウルトラ2−wayfitですが、サカタニ滝谷駅前店の店長さんに相談した所、リムを交換することになりました。
そしてタイヤもバーストしてしまったので交換しなければなりません。
はじめは使い慣れていて耐久性も高いコンチネンタル・グランプリ4000sにしようと思っていました。
ところが、店長のカツさんから「チューブレス兼用ホイールは、チューブレスタイヤを履かせるべき」とアドバイスを受けたので、初めてチューブレスタイヤを採用することにあいなったのです。
チューブレスタイヤのデメリットである装着性の悪さも、カツさんに装着してもらうので無問題。
どのタイヤにするのかはカツさんにお任せすることにして、それまでの間はR500で修行の旅。
乗鞍に向けて出発する前日、前後輪ともチューブレスタイヤが装着された状態のシャマルウルトラとご対面。
同時に、後輪のフレ取りと、ハブのグリスアップもお願いしていたので、実質的にはホイールのフルメンテナンスと言っても過言ではありません。
↓乗鞍の山頂で六甲おろしを歌唱する。

このとき、クアトロはチェーンを取り外していたので、電動アルテグラのチェックはできませんでした。
でも、「もし、明日、試走してみて調子が悪ければ、宿まで持ってきて。」と言ってもらっていたので不安に思うことはありません。
というわけで、乗鞍ヒルクライムの前日、チューブレスタイヤのシェイクダウン。
実際、チューブレスタイヤで走ってみると、とても不思議な感じ。
走行するときの抵抗感が感じられないというか、とても軽いんですよね。
私の場合、タイヤの空気圧は8気圧なのですが、リム打ちパンクのリスクが無いチューブレスも同じ8気圧に設定。
タイヤの気圧を高くすればするほど走行感が軽くなると思っていたのですが、高すぎると路面の接地性が低くなるので良くないそうです。
8気圧の場合、細かな段差でも振動となってハンドルに伝わってくるのですが、チューブレスの場合、「まったり」とした振動で伝わって来ました。
チューブレスは乗り心地が良いと言いますが、それはタイヤの空気圧を低くしても走れるためだと思っていたのです。
けれども、同じ8気圧でもチューブレスのほうが乗り心地が良かったのは想定外のメリット。
そしてレース本番。
ヒルクライムの登りもやっぱり軽い印象を受けました。
具体的に言うと、「このくらい回せば、このくらい進む」というのが誰にでもあると思うんですが、自分が思っている進み具合よりも+10%進むって感じでしょうか。
↓さあ、行ってきます。

早朝ヒルクライム自転車通勤でも使用したいのですが、あくまでシャマルウルトラは“決戦用”。
次のレースまでは封印しなければなりません。
というわけで、普段はR500を使うことにしました。
もし、落車したり、バーストしてホイールがお釈迦になってもR500だと精神的なダメージも、お財布のダメージも少ないでしょう。
それに、来年の乗鞍ヒルクライムで1時間ヒトケタ台を目指すためには、R500で自らに負荷をかけて鍛えあげなければなりません。
昔、少林寺三十六房という映画がありましたが、大阪府の秘境金剛山金剛寺に実在するという昼暗夢三十六房。
その第1房“鉄輪房”では、鋼鉄で組み上げられた車輪をひたすら回し、その心身を鍛え上げられるとか。(出典:民明書房刊「日本にも実在した少林寺三十六房」
というわけで、明日から前後輪とも鉄下駄R500を履いて一から出直します。
自転車ブログ集を見るならここをクリック
ロードバイクブログ集を見るならここをクリック
自転車ブログ集を見るならここをクリック
ランキングに参加しています。押して頂けると、更新のモチベーションが上がります!お手数ですがポチッっとクリックお願いします。