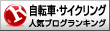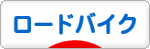ガリガリ君リッチ・コーンポタージュ味を食べてみたところ、意外に常識的なお味だったことに「これでは、罰ゲームアイテムにならへんなぁ〜」ちょっと物足りなさを感じてしまった、たーちゃんです。おはようございます。
自転車ブログ集を見るならここをクリック(自転車ブログ村)
ロードバイクブログ集を見るならここをクリック(ロードバイクブログ村)
自転車ブログ集を見るならここをクリック(自転車ブログランキング)
そんなガリガリ君リッチ‥コーンポタージュ味(以下、ガリーポッターと略す)も、想定外の売れ行きで、生産量が間に合わないことから発売を給しているとか。
“販売休止作戦”でさらに話題を集めるマーケティング戦略かもしれませんが、これほどまで話題にあがるガリガリ君は前代未聞。
ガリーポッターが発売された直後は、ツイッターでもタイムラインに頻繁に登場していました。
その一方、ネットで情報を得る頻度が低い私の職場のめんめんは「えっ、なにそれ?」って淡白な反応。
もし、ネットなるものがこの世に無ければ、ガリーポッターは単なる“キワモノ商品”として人知れずこの世に出て、消え去っていたことでしょう。
商品が話題を集め、売れるか売れないのかは、その品質や内容よりもネットでどれだけ話題を集めるのかが大事なんですね。
真に優れた製品やサービスを開発する努力を払うよりも、ネットで小手先のマーケティング戦略がうまいこと行けば売れてしまうのです。
私も、そんな小手先のマーケティング戦略に乗せられた一人ですが・・・・
これでは、いい仕事をしようとか、優れた商品を世に出したいというモチベーションが下がってしまうのは仕方ないのかもしれません。
最近、わが国の国際競争力が10位に転落しましたが、その原因としては「いい仕事をしよう」と言う情熱が失われてしまったことにあると思うのですが、いかがでしょうか?
さて、肝心のガリーポッターのお味ですが、塩味が控えめであっさりしたコーンポタージュって感じ。
コア(核)部分のシャーベットにはつぶつぶコーンが入っているのですが、東鳩キャラメルコーンのピーナッツみたいに無くても良かったのでは。
そのお味は食べられないことはありませんが、炎天下の中、汗を流しながらロードバイクで走り終え、ようやくたどり着いたコンビニのアイスクリームコーナーで見かけたとしても、手に取ることは無いだろう・・・って感じですな。
まあ、このブログはガリガリ君ブログではないので、さっそく前回のブログの続きからお話します。
(今回のルート図&走行データはここをクリック)
↓この小さなトンネルを超えると秘境が始まります。
![]()
旧モーソンは奈良の秘湯“洞川温泉”と秘境「行者還」との分岐点。
洞川温泉は観光客も通るので2車線のキレイな道路ですが、秘境「行者還」に向かう道は分岐点から幅員が3mにも満たない荒れた道になります。
もちろん、私がセレクトしたのは、「行者還」に向かう荒れた道。
国道ならぬ酷道309号は右手にクリスタルのような透明度が高い川を見下ろしながら、ゆるやかな登り坂が延々続き、美しくも寂しい秘境へ誘います。
路面は荒れており、砂利や落ち葉が落ちているので、スピードを落として淡々と走り続けます。
分岐から行者還までは23kmほどあるのですが、昨年の台風被害からの復旧工事の際、「秘境の終わり」までの距離表示板が設置されました。
昨年の春、同じルートを走ったのですが、行き交う自動車は1台もなく、聞こえるのは谷川の流れと、風の音だけ。
そんな秘境を、どれだけ走れば脱出できるのか分かるということは、メンタル面でも助かるというもの。
“おひとりさま”サイクリストはマイペースで気軽に走ることができるのが魅力である反面、何かあったときも“おひとりさま”で解決しなければなりません。
行き交う自動車は1時間に1台あるかどうか・・・・そんな中で落車して大怪我をすれば、それは交通事故というよりも、もはや「遭難」に近いものがあります。
奈良の秘境ですから、携帯電話はつながらないでしょう。
よしんば繋がったとしても、救急車がやってくるまで数時間は要するかもしれません。
道路外に転落して気を失ったら、奈良の秘境には未だ生息していると言われるニホンオオカミや、森のくまさんなどの「森の仲間」に生きたまま食われてしまうおそれもあります。
ゆえに、天川村から行者還を抜けて奈良の再奥部である上北山村に抜ける酷道309号を自転車で走ることは危ないのでやめたほうが良いと言われました。
昨年の春は、いたるところに残雪が残り、山肌もあらわになって荒涼とした寂しい酷道を一人黙々と登っているときは、「人の忠告は素直に聞き入れるべきだ」と思ったものの・・・
大峰山脈の険しくも雄大な山容を目の当たりにした時、都会である大阪府から半径100km以内にかくも素晴らしい風景を見ることができるなんてと感激してしまい、もう一度来たいと思っていたのです。
そう、このとき私は「秘境」の魅力にとり憑かれてしまったのです。
↓雄大な山々を眺めながら登っていきます。
![]()
「秘境」を一人で走っているときは、寂しいものがあります。
ヒルクライムレースや総決起集会と違って、楽しさや苦しさ、そして充実感を共有できる自転車仲間はそこにはいません。
しかし、一人で秘境を乗り越えたときに得られることは何物にも代えがたい魅力があるのです。
リスクを回避しながら、目的地に到達する過程はまさに「冒険」。
家族を養うサラリーマンが「冒険」できる機会というのはどれほどあるでしょうか?
そんな「冒険」とは、非日常を体験し、日々のマンネリ化して刺激がないのに、ストレスは溜まる一方というつまらない日々をリセットして、生き生きとしたものへと変化させる触媒であるのです。
これだから、ヒルクライムレースや総決起集会に加えて、おひとりさまロングライドもやめられないんですよね。
ただ、まだ残暑きびしい初秋の候、大峰山脈は緑で覆われ、荒涼と言うよりも優雅って感じ。
さらに、早朝ヒルクライム自転車通勤のおかげか、体力がついてしまい、思ったよりも簡単に秘境脱出成功。
アウター縛りで完走することができました。
全長1151m、まったく照明がない漆黒の「行者還トンネル」。
↓全長1151mもありながら、照明がまったくない「行者還トンネル」。
![]()
そのトンネルは照明はまったくないだけでなく、反射板もなく、路面に白線も書いていないので、上下左右がまったくわからない。
そんな暗闇のなかをロードバイクで走っていると方向感覚が狂ってきて不思議な感覚。
トンネルを通過して下り坂を下り終えると、そこは人跡未踏の秘境の果てにある奈良県上北山村。
日本有数の難易度を誇りながら、そのホスピタリティーは最高である「ヒルクライム大台ケ原」の開催地であります。
エントリー費は7,000円と標準的ですが、アミノバイタルは飲み放題、ゴール後のそうめんは食べ放題、そして500円の村内お買い物券つき。
今回は、私は仕事のためエントリーしたもののDNSと相成りましたが、僅少ではございますが、上北山村のご発展にお役立てください。
そう、村内には「ヒルクライム大台ケ原」のノボリがあちこちに立てられていて、住民の方がこのイベントを盛り上げようという意気込みがひしひしと伝わって来ました。
他のヒルクライムレースと違って、このヒルクライム大台ケ原ほど、住民の応援が心あたたまるものはなく、ゴールして下山した時、思わず目頭が熱くなったのを今でも忘れることはできません。
↓いたるところにノボリが立てられ、盛り上がる上北山村。
![]()
私がもっとも楽しみにしていたヒルクライムレースはこの「大台ケ原ヒルクライム」で、このレースが私の自転車生活にとって大きな支えとなっています。
しかしながら、この日は突然のお仕事。
重要な仕事であるなら仕方ないと諦めることもできますが、その内容は人数合わせの帳尻合わせ的業務。
自分の部署の担当業務ならともかく、ヨソの部署の応援の休日出勤。
レース当日に仕事が重なったときは本当にショックでした。
そんな私は一瞬ではありませんが、これから先、自転車に乗理続けるモチベーションが下がってしまったのです。
何のために、真冬の寒風吹きすさぶ中、夜明け前の酷寒の中、凍える指先の痛さに耐えながら堺浜をグルグル回ったのか・・・
午前4時30分に自宅を出発して、流れる汗を拭いながら山々を登ったのは何のためだったか、わからなくなりました。
サラリーマンサイクリストですから、それらをグッと飲み込まなければならないことは言うまでもありませんが、下がったモチベーションをどうやって持ち直したら良いのか・・・
そう、もともと私は“おひとりさまロングライダー”・・・原点に戻って見ることにしました。
レースが終わり冬が始まるまではロングライドシーズンの到来。
最近はヒルクライムを主眼において活動していたので、ロングライドをする機会は少なかったのです。
そこで、自転車生活の魅力に取り付かれたロングライドをもう一度やってみれば、失われつつあるモチベーションを復活できるのでは・・・と思ったのが今回の山岳ロングライド。
秘境を通過し、数日後、開催されるであろうヒルクライム大台ケ原のスタート地点に立った時、失われつつあるモチベーションが少しづつではありますが、取り戻せたような気がするのです。
さて、上北山村にお住まいのブログ仲間「エリザベス」さんにメールを送った後(スマホを持っていないのでリアルタイムのツイッターはできないのです・・・)、大台ケ原ヒルクライムレースコーススタート。
この時点で100km以上走っているので、もうタイムを競うつもりは無く、マイペースで走っていきます。
数日後、ここと同じ道を数百人のヒルクライマーが一斉にスタートを切り、約7kmの平坦区間を集団走行で駆け抜けていくのですが、今日は私一人でボチボチ走ります。
↓大台ケ原に到着。
![]()
小処温泉との分岐から激坂が始まりますが、普通のヒルクライムコースの場合、激坂は一時的なガマンで乗り越えることができるものの、ここでは13km以上延々と続きます。
昨年のレースでは、永遠に終わることがない激坂に絶望感すら感じたのですが、レースですから足をつくことなんてできず、まさに拷問だったのを覚えています。
今回は、すでに100km以上走り続けている上、レースでもトレーニングでもなく、写真を撮るという名目で足を着いても何ら恥じるものではありません。
しかし、そこはヒルクライマーの末席を汚すものとしての最低限のプライドが許さず、フロントはインナーですが、リアはローから3番目ぐらいのギアでゆっくり登ります。
苦痛が快楽と感じることができる方には魅力的なコースですが、ロードバイクに乗り始めてから半年も満たなかった私が、こんなハードなレースコースをよく走ったなぁ〜と感心した次第です。
13kmの激坂が終わると大台ケ原ドライブウェイに合流。
アップダウンを繰り返した後、ゴールの大台ケ原駐車場に到着。
数日後、ここでは食べ放題のそうめんが振舞われ、配られた冷たい大台ケ原の水で喉を潤しながら、お互いの健闘をたたえ合うヒルクライマーが集うのですが、この日のヒルクライマーは私一人。
お疲れ様〜って、言うこともなければ、言われることもありませんが、大台ケ原まで登ってきたのは間違いありません。
このときは、寂しさよりも、達成感や充実感、そして爽快感こそ感じていたのですが、寂寥感や孤独感なんてまったく感じなかったのです。
ヒルクライムレースに出てから、レースの楽しさに夢中になりすぎていたのか、もともとは山を自転車で登ること自体、愛していたことを思い出すことができたのでしょうか?
だとすれば、今回の山岳ロングライドは大成功といえるでしょう。
1年で366日雨が降ると言われる大台ケ原はみるみるうちに曇ってきて肌寒くなるところに秋の気配が感じられます。
3年前、ユニクロで買ったウインドブレーカーを着て、下山開始。
来年こそ、自転車生活が続けることができ、大台ケ原ヒルクライムに参戦できることを祈りつつ、静かな大台ケ原を後にした、たーちゃんなのでした。
自転車ブログ集を見るならここをクリック
ロードバイクブログ集を見るならここをクリック
自転車ブログ集を見るならここをクリック
ランキングに参加しています。押して頂けると、更新のモチベーションが上がります!お手数ですがポチッっとクリックお願いします。
![にほんブログ村 自転車ブログへ]()
![人気ブログランキングへ]()
![にほんブログ村 自転車ブログ ロードバイクへ]()
自転車ブログ集を見るならここをクリック(自転車ブログ村)
ロードバイクブログ集を見るならここをクリック(ロードバイクブログ村)
自転車ブログ集を見るならここをクリック(自転車ブログランキング)
そんなガリガリ君リッチ‥コーンポタージュ味(以下、ガリーポッターと略す)も、想定外の売れ行きで、生産量が間に合わないことから発売を給しているとか。
“販売休止作戦”でさらに話題を集めるマーケティング戦略かもしれませんが、これほどまで話題にあがるガリガリ君は前代未聞。
ガリーポッターが発売された直後は、ツイッターでもタイムラインに頻繁に登場していました。
その一方、ネットで情報を得る頻度が低い私の職場のめんめんは「えっ、なにそれ?」って淡白な反応。
もし、ネットなるものがこの世に無ければ、ガリーポッターは単なる“キワモノ商品”として人知れずこの世に出て、消え去っていたことでしょう。
商品が話題を集め、売れるか売れないのかは、その品質や内容よりもネットでどれだけ話題を集めるのかが大事なんですね。
真に優れた製品やサービスを開発する努力を払うよりも、ネットで小手先のマーケティング戦略がうまいこと行けば売れてしまうのです。
私も、そんな小手先のマーケティング戦略に乗せられた一人ですが・・・・
これでは、いい仕事をしようとか、優れた商品を世に出したいというモチベーションが下がってしまうのは仕方ないのかもしれません。
最近、わが国の国際競争力が10位に転落しましたが、その原因としては「いい仕事をしよう」と言う情熱が失われてしまったことにあると思うのですが、いかがでしょうか?
さて、肝心のガリーポッターのお味ですが、塩味が控えめであっさりしたコーンポタージュって感じ。
コア(核)部分のシャーベットにはつぶつぶコーンが入っているのですが、東鳩キャラメルコーンのピーナッツみたいに無くても良かったのでは。
そのお味は食べられないことはありませんが、炎天下の中、汗を流しながらロードバイクで走り終え、ようやくたどり着いたコンビニのアイスクリームコーナーで見かけたとしても、手に取ることは無いだろう・・・って感じですな。
まあ、このブログはガリガリ君ブログではないので、さっそく前回のブログの続きからお話します。
(今回のルート図&走行データはここをクリック)
↓この小さなトンネルを超えると秘境が始まります。

旧モーソンは奈良の秘湯“洞川温泉”と秘境「行者還」との分岐点。
洞川温泉は観光客も通るので2車線のキレイな道路ですが、秘境「行者還」に向かう道は分岐点から幅員が3mにも満たない荒れた道になります。
もちろん、私がセレクトしたのは、「行者還」に向かう荒れた道。
国道ならぬ酷道309号は右手にクリスタルのような透明度が高い川を見下ろしながら、ゆるやかな登り坂が延々続き、美しくも寂しい秘境へ誘います。
路面は荒れており、砂利や落ち葉が落ちているので、スピードを落として淡々と走り続けます。
分岐から行者還までは23kmほどあるのですが、昨年の台風被害からの復旧工事の際、「秘境の終わり」までの距離表示板が設置されました。
昨年の春、同じルートを走ったのですが、行き交う自動車は1台もなく、聞こえるのは谷川の流れと、風の音だけ。
そんな秘境を、どれだけ走れば脱出できるのか分かるということは、メンタル面でも助かるというもの。
“おひとりさま”サイクリストはマイペースで気軽に走ることができるのが魅力である反面、何かあったときも“おひとりさま”で解決しなければなりません。
行き交う自動車は1時間に1台あるかどうか・・・・そんな中で落車して大怪我をすれば、それは交通事故というよりも、もはや「遭難」に近いものがあります。
奈良の秘境ですから、携帯電話はつながらないでしょう。
よしんば繋がったとしても、救急車がやってくるまで数時間は要するかもしれません。
道路外に転落して気を失ったら、奈良の秘境には未だ生息していると言われるニホンオオカミや、森のくまさんなどの「森の仲間」に生きたまま食われてしまうおそれもあります。
ゆえに、天川村から行者還を抜けて奈良の再奥部である上北山村に抜ける酷道309号を自転車で走ることは危ないのでやめたほうが良いと言われました。
昨年の春は、いたるところに残雪が残り、山肌もあらわになって荒涼とした寂しい酷道を一人黙々と登っているときは、「人の忠告は素直に聞き入れるべきだ」と思ったものの・・・
大峰山脈の険しくも雄大な山容を目の当たりにした時、都会である大阪府から半径100km以内にかくも素晴らしい風景を見ることができるなんてと感激してしまい、もう一度来たいと思っていたのです。
そう、このとき私は「秘境」の魅力にとり憑かれてしまったのです。
↓雄大な山々を眺めながら登っていきます。

「秘境」を一人で走っているときは、寂しいものがあります。
ヒルクライムレースや総決起集会と違って、楽しさや苦しさ、そして充実感を共有できる自転車仲間はそこにはいません。
しかし、一人で秘境を乗り越えたときに得られることは何物にも代えがたい魅力があるのです。
リスクを回避しながら、目的地に到達する過程はまさに「冒険」。
家族を養うサラリーマンが「冒険」できる機会というのはどれほどあるでしょうか?
そんな「冒険」とは、非日常を体験し、日々のマンネリ化して刺激がないのに、ストレスは溜まる一方というつまらない日々をリセットして、生き生きとしたものへと変化させる触媒であるのです。
これだから、ヒルクライムレースや総決起集会に加えて、おひとりさまロングライドもやめられないんですよね。
ただ、まだ残暑きびしい初秋の候、大峰山脈は緑で覆われ、荒涼と言うよりも優雅って感じ。
さらに、早朝ヒルクライム自転車通勤のおかげか、体力がついてしまい、思ったよりも簡単に秘境脱出成功。
アウター縛りで完走することができました。
全長1151m、まったく照明がない漆黒の「行者還トンネル」。
↓全長1151mもありながら、照明がまったくない「行者還トンネル」。

そのトンネルは照明はまったくないだけでなく、反射板もなく、路面に白線も書いていないので、上下左右がまったくわからない。
そんな暗闇のなかをロードバイクで走っていると方向感覚が狂ってきて不思議な感覚。
トンネルを通過して下り坂を下り終えると、そこは人跡未踏の秘境の果てにある奈良県上北山村。
日本有数の難易度を誇りながら、そのホスピタリティーは最高である「ヒルクライム大台ケ原」の開催地であります。
エントリー費は7,000円と標準的ですが、アミノバイタルは飲み放題、ゴール後のそうめんは食べ放題、そして500円の村内お買い物券つき。
今回は、私は仕事のためエントリーしたもののDNSと相成りましたが、僅少ではございますが、上北山村のご発展にお役立てください。
そう、村内には「ヒルクライム大台ケ原」のノボリがあちこちに立てられていて、住民の方がこのイベントを盛り上げようという意気込みがひしひしと伝わって来ました。
他のヒルクライムレースと違って、このヒルクライム大台ケ原ほど、住民の応援が心あたたまるものはなく、ゴールして下山した時、思わず目頭が熱くなったのを今でも忘れることはできません。
↓いたるところにノボリが立てられ、盛り上がる上北山村。

私がもっとも楽しみにしていたヒルクライムレースはこの「大台ケ原ヒルクライム」で、このレースが私の自転車生活にとって大きな支えとなっています。
しかしながら、この日は突然のお仕事。
重要な仕事であるなら仕方ないと諦めることもできますが、その内容は人数合わせの帳尻合わせ的業務。
自分の部署の担当業務ならともかく、ヨソの部署の応援の休日出勤。
レース当日に仕事が重なったときは本当にショックでした。
そんな私は一瞬ではありませんが、これから先、自転車に乗理続けるモチベーションが下がってしまったのです。
何のために、真冬の寒風吹きすさぶ中、夜明け前の酷寒の中、凍える指先の痛さに耐えながら堺浜をグルグル回ったのか・・・
午前4時30分に自宅を出発して、流れる汗を拭いながら山々を登ったのは何のためだったか、わからなくなりました。
サラリーマンサイクリストですから、それらをグッと飲み込まなければならないことは言うまでもありませんが、下がったモチベーションをどうやって持ち直したら良いのか・・・
そう、もともと私は“おひとりさまロングライダー”・・・原点に戻って見ることにしました。
レースが終わり冬が始まるまではロングライドシーズンの到来。
最近はヒルクライムを主眼において活動していたので、ロングライドをする機会は少なかったのです。
そこで、自転車生活の魅力に取り付かれたロングライドをもう一度やってみれば、失われつつあるモチベーションを復活できるのでは・・・と思ったのが今回の山岳ロングライド。
秘境を通過し、数日後、開催されるであろうヒルクライム大台ケ原のスタート地点に立った時、失われつつあるモチベーションが少しづつではありますが、取り戻せたような気がするのです。
さて、上北山村にお住まいのブログ仲間「エリザベス」さんにメールを送った後(スマホを持っていないのでリアルタイムのツイッターはできないのです・・・)、大台ケ原ヒルクライムレースコーススタート。
この時点で100km以上走っているので、もうタイムを競うつもりは無く、マイペースで走っていきます。
数日後、ここと同じ道を数百人のヒルクライマーが一斉にスタートを切り、約7kmの平坦区間を集団走行で駆け抜けていくのですが、今日は私一人でボチボチ走ります。
↓大台ケ原に到着。

小処温泉との分岐から激坂が始まりますが、普通のヒルクライムコースの場合、激坂は一時的なガマンで乗り越えることができるものの、ここでは13km以上延々と続きます。
昨年のレースでは、永遠に終わることがない激坂に絶望感すら感じたのですが、レースですから足をつくことなんてできず、まさに拷問だったのを覚えています。
今回は、すでに100km以上走り続けている上、レースでもトレーニングでもなく、写真を撮るという名目で足を着いても何ら恥じるものではありません。
しかし、そこはヒルクライマーの末席を汚すものとしての最低限のプライドが許さず、フロントはインナーですが、リアはローから3番目ぐらいのギアでゆっくり登ります。
苦痛が快楽と感じることができる方には魅力的なコースですが、ロードバイクに乗り始めてから半年も満たなかった私が、こんなハードなレースコースをよく走ったなぁ〜と感心した次第です。
13kmの激坂が終わると大台ケ原ドライブウェイに合流。
アップダウンを繰り返した後、ゴールの大台ケ原駐車場に到着。
数日後、ここでは食べ放題のそうめんが振舞われ、配られた冷たい大台ケ原の水で喉を潤しながら、お互いの健闘をたたえ合うヒルクライマーが集うのですが、この日のヒルクライマーは私一人。
お疲れ様〜って、言うこともなければ、言われることもありませんが、大台ケ原まで登ってきたのは間違いありません。
このときは、寂しさよりも、達成感や充実感、そして爽快感こそ感じていたのですが、寂寥感や孤独感なんてまったく感じなかったのです。
ヒルクライムレースに出てから、レースの楽しさに夢中になりすぎていたのか、もともとは山を自転車で登ること自体、愛していたことを思い出すことができたのでしょうか?
だとすれば、今回の山岳ロングライドは大成功といえるでしょう。
1年で366日雨が降ると言われる大台ケ原はみるみるうちに曇ってきて肌寒くなるところに秋の気配が感じられます。
3年前、ユニクロで買ったウインドブレーカーを着て、下山開始。
来年こそ、自転車生活が続けることができ、大台ケ原ヒルクライムに参戦できることを祈りつつ、静かな大台ケ原を後にした、たーちゃんなのでした。
自転車ブログ集を見るならここをクリック
ロードバイクブログ集を見るならここをクリック
自転車ブログ集を見るならここをクリック
ランキングに参加しています。押して頂けると、更新のモチベーションが上がります!お手数ですがポチッっとクリックお願いします。